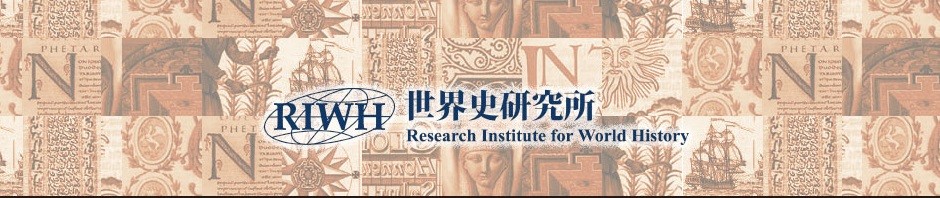1.発端・・・2025年11月7日、高市首相は衆議院予算委員会の質疑で台湾に対する中国の軍事攻撃を日本の「存立危機事態」とする答弁を行った。それに対して中国側は「内政干渉」として激しく反発し、日中関係は一挙に険悪な状況に陥っている。この高市発言は、2015年に成立した安全保障法制に照らして法的に妥当するものなのか、また、米中関係の現状からして果たしてリアリティのある発言なのか、検証してみたい。
高市首相の問題発言とは次のようなものである。「軍艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態にはなりうるケースであると私は考える」(『朝日』2025年11月19日)。
ここでいう「存立危機事態」は、「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の第二条4項でこう規定されている。「我が国と密接に関係のある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」とされている。
2.法的問題点・・・この規定による「我が国と密接に関係のある他国」とは台湾危機の場合でいえば、米国であると考えられる。つまり、台湾が独立を宣言し、これに反対する中国が武力で介入したことに対して、米軍が台湾を擁護するために軍事介入した事態を日本の「存立危機事態」と解釈しているのである。
この主張の第一の問題は、1972年に日中が国交回復した際の共同声明で、中国側が「台湾は中国の不可分の領土である」と表明したことに対して、日本側は「十分理解し、尊重する」と表明していたこととの関連である。つまり、日本政府は、中国本土との国交回復にあたり、台湾が中国に帰属するという「一つの中国」論を受け入れていたのであり、今さら台湾の独立支持論に転換するのは自らの公約に反することになる。
関連して、日本では、ロシアのウクライナ侵略と中国の台湾への軍事攻撃を同類のものとして論じる向きがあるが、ウクライナは明確に独立国であるのに対し、台湾は「中国の一部」として日本は認めてきたので、この類推はそもそも成り立たない。むしろ、ウクライナ侵略によってロシアも多大な犠牲を被っている事態が中国に台湾に対する軍事侵攻を自制させる効果をもつと考える方が自然ではないだろうか。
第二の問題点は、近年の台湾で実施された世論調査によると、当事者である台湾の人々の約6割は「現状維持」を希望しており、独立支持は3割にとどまる点である(南塚信吾ほか『軍事力で平和は守れるか』岩波書店。2023年、p.238)。台湾が独立を宣言すれば、中国の軍事介入を招き、最も大きな犠牲を被るのは台湾の人々であることを台湾の人々は十二分に予想しているがゆえにこのような結果が出ているのである。このような台湾の世論状況を無視して、台湾独立を前提にして軍事的危機を煽る議論を行うのは台湾危機を利用して日本の軍拡を推進する者のためにする議論と言わなければならない。
第三の問題点は、台湾で軍事紛争が発生した場合に、米軍が軍事介入する可能性がどれだけあるのか、という点である。米国には台湾関係法(1979年制定)があり、台湾への「防御的武器供給」の規定はあるが、米軍の参戦規定はない。それ故、米軍が参戦する場合には、改めて米国議会に承認を得ることが必要になるが、この間のアフガニスタンやイラクでの「対テロ戦争」に嫌気がさしてきた議員たちが簡単に派兵を承認するか、疑問である。とくに、「アメリカ・ファースト」を主張するトランプ政権は、最近、経済的利害を重視して、対中接近を優先する外交を見せているだけに、台湾問題で対中戦争に踏み切る覚悟があるのか、はなはだ疑問である。この点は現在の東アジア情勢の検討から後により詳しく検討したい。
第四に、「存立危機事態」は、日米安全保障条約で同盟関係にある米国が台湾危機に軍事介入した場合に発生するもので、米軍なしで日本だけ単独介入する根拠にはならない。高市発言はその点を曖昧にして、台湾危機があたかも日本「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される事態」であるかのように主張するのは著しい飛躍といわなければならない。台湾の情勢がなぜ日本国民の生命や自由」などに危機を及ぼすのか、きちんと説明すべきである。
3.昨今の東アジア情勢から見た問題点・・・高市発言の前提には、台湾に中国が軍事介入した場合、米軍が台湾防衛のために軍事介入するということが自明のこととして考えられているが、その前提は昨今のトランプ政権の対中国政策の動向から妥当なものといえるのだろうか。
この点に関する第一の問題は、2025年11月にホワイト・ハウスが発表した『国家安全保障戦略』文書との関連である。この文書では、「モンロー・ドクトリンのトランプ系論(Corollary)」として西半球を米国の安全保障に密接にかかわる地域として重視する姿勢を明確にして、勢力圏分割的な姿勢を明示している。また、インド太平洋地域に関しては、そこが世界の名目GDPの半分くらいを占める成長地域であることを指摘した上で「長期的に、米国の経済的・技術的優越性を維持する確実な道は大規模な軍事衝突を抑止し、防止すること」と明記している。その上で、台湾については、「軍事的な優位を維持することにより、台湾をめぐる紛争を抑止することが第一である。・・・米国は、台湾海峡の現状の一方的な変更支持しない」と述べている。
また、他の所で、トランプ政権は、中国の市場開放をめざした、従来の対中政策が失敗だったと指摘し、「米国の経済的独立を回復するために、相互性や公平性を優先することにより、中国との経済関係をリバランスする」と主張し、そのためにも、「インド太平洋における戦争の抑止に、明確で絶えることのない焦点を当てる」ことを強調している。
つまり、第二次トランプ政権は、何よりも中国との経済的な「リバランス」を追求し、インド太平洋における戦争の抑止を重視しているのであり、その前のバイデン政権と比較すると、中国とのイデオロギーや安全保障戦略上の対抗より、経済的な利害調整を重視する姿勢を強めている。
その結果、10月9日には、中国が米国からの農産物輸入の代わりに、レアアースの供給停止を1年間停止する合意が成立した。また、10月末のアジア太平洋経済協力会議の折に行われた米中首脳会議では、半導体輸出関税を18ケ月間保留することで合意し、目下、米中間は関税戦争を停止して、歩み寄りの姿勢を見せているのである。そのような折に、台湾の軍事紛争に米軍が介入することを前提する「台湾有事論」を提起するというのは、全く東アジア情勢の展開を知らない情報オンチの発言か、または、意図的に東アジアの緊張激化を醸成しようとするためにする発言としか思えないのである。
第二に、以上のような米中接近の現状との関連で、高市首相の「台湾有事」発言はトランプ政権にとっては不都合なものであり、11月25日には、トランプ大統領と高市首相の電話会談が米国からの要請で行われた。その場で、トランプは、前日に行われた習近平との電話会談で「米国側は中国にとっての台湾問題の重要性を理解する」と発言したことを高市に伝えたという。来年4月に習近平の訪米を予定している米中間では、米中対立を激化させる争点の浮上は避けたい意向が浮上しているのであり、それに逆らう高市発言はむしろトランプ政権からさえ警戒されるものであった。それが11月25日に日米の電話会談が急遽行われた理由であろう。
トランプ大統領の発言には、一貫性がないので、この対中宥和姿勢が何時迄続くのか不確定な面があるが、少なくとも東アジア情勢の緊張緩和を促進する効果を持つのは確かだろう。この機会を利用して日中も緊張緩和を促進するのが日本にとっても利益になるのではないだろうか。しかも、10月30日にはやはりアジア太平洋経済協力会議の機会を利用して日中首脳会談が実現したのであるから、その機会を日中間の緊張緩和促進に持ってゆくべきだったのに、その1週間後に官僚の用意した答弁書にはなかった「台湾有事論」を個人プレイとして発言するとはどういうことであろうか。政治家としての情勢認識力を疑わざるを得ない。または、米中の緊張緩和に抵抗する対中強硬論者の「確信犯」的発言だったのか、心配になる発言であった。
日本の世論調査では、高市発言を今のところ支持する世論が多いと聞くが、一時的な嫌中感情に流されず、法的や情勢論的な問題点を冷静に検討する姿勢が広まることを期待したい。