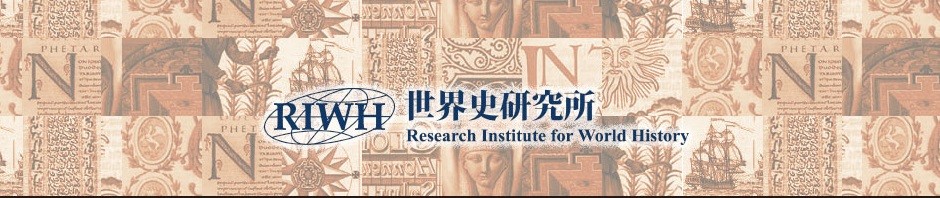2025年6月13日、イスラエルが突然イランの核関連施設や軍事関連の人と場所を攻撃しはじめた。すぐにイランも反撃し、双方の攻撃が続いた。この問題をめぐって、ネット上に登場した日本の主要新聞の「社説」「主張」を比較点検してみた。比較したのは、ネット上で取りやすい日本経済新聞6月13日社説、読売新聞6月14日社説、産経新聞6月14日主張、信濃毎日新聞6月14日社説、東京新聞6月14日社説、朝日新聞6月14日社説、しんぶん赤旗6月15日主張、毎日新聞6月17日社説、西日本新聞6月17日社説である。
論点は多岐にわたるが、以下では主なものについてのみ、検討の対象としている。
1. 国連憲章との関係について
(1)明白な違反
イスラエルのイラン攻撃が国連憲章への明白な違反であると主張しているのは、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、それに赤旗である。この場合、国連憲章というのは、戦後の国際秩序ということも含めている。この他の新聞は、イスラエルの攻撃は国連憲章への違反だという批判はしていない。しかし、信濃毎日新聞などは、国連憲章違反だとは言わないが、イスラエルの「無謀な軍事行動」を「強く批判」した。赤旗は、イランを不法に攻撃するイスラエルを「制裁」せよとまで主張している。
(2)国連憲章と「自衛権」
一主権国家が他の主権国家を武力攻撃するというのは、国連憲章に認められた「自衛権」の行使以外にはありえない(例外的に、国連安保理の決定による場合があるが)。
国連憲章はその第51条において、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」と規定している。
イスラエルは今度の攻撃は、そういう「自衛権」の行使であると主張している(ちなみにイスラエルはガザ地区の攻撃についても「自衛権」の行使であると主張している)。では、今回イスラエルの言う「自衛権」というのは成り立つのかどうかという問題がある。
2. イランの核兵器開発について
(1)核開発の脅威と「自衛権」
では、イランの核兵器開発を理由に、軍事攻撃はできるのだろうか。イスラエルは、イランの核開発が自国の安全保障上の脅威であるから、それを阻止するために「自衛」のための攻撃をしたとしている。
これを認めているのが産経新聞である。同紙は、①イランは数日間で核兵器級の濃縮が可能な水準に達していた、➁国際原子力機関(IAEA)理事会は、6月12日IAEAとの査察協定に反しているとイランを非難する決議を採択した、③イランが核兵器を手にすれば親イラン武装勢力に渡ってイスラエル攻撃に使用する恐れがあると、主張して、イスラエルの攻撃を容認したわけである。そのうえで、「最大限の自制」を関係国に求めた。
一方、イスラエルは、イランの核開発は「自国の生存への脅威だ」と主張し、国際法で原則禁止されている先制攻撃を正当化するが、これについては、危機が差し迫っているわけではないので「自衛」ということは当てはまらないというのが、朝日新聞、毎日新聞、赤旗の主張である。毎日新聞は、自衛権を認めていないという意味で、イスラエルの攻撃が国連憲章違反だとしていると考えられる。また(、)イスラエルの主張は「自衛権の拡大解釈」で「危うい」とするのが日本経済新聞である。東京新聞もイスラエルの主張は「とても受け入れられない」と批判している。
読売新聞はこの問題を避けているようである。
(2)イランの核保有について
イランが核兵器を保有しているかどうかという点については、どの新聞も確定できていない。いわば伝聞で終わっている。だが微妙な違いがある。
一番確定的なことを述べているのが、「核弾頭9発分の高濃縮ウランを製造し、兵器化の段階に入っていると指摘されている」という西日本新聞で、同じく、イランがウランを濃縮して「核爆弾9個分に相当するウランを持つとされる」とするのが読売新聞である。ともに「核弾頭9発分」という数字を出している。
これに対し、イスラエルは、イランが「平和利用」を隠れみのに、核兵器を開発していると「主張する」として、漠然とした伝聞で終わっているのが毎日新聞である。
高濃縮ウランの製造までで話を止めている新聞もある。日本経済新聞は、イランが「核兵器をつくらないと公言しながら、核爆弾に使えるレベルの高濃縮ウランをため込むのは理解に苦しむ。」とし、イランは自ら核について真相を明らかにすべきであると、注文している。東京新聞も、「ウラン濃縮活動」のみを確認するにとどめている。
イランの核保有に懐疑的なのが朝日新聞で、「確かに、イランは原発用の燃料などよりはるかに高い濃度のウラン保有量を増やしてきた。ただ、核兵器を持つ意思はないと繰り返し強調し、国際機関も兵器級までの濃縮は確認していない。」とする。
(3)イランとアメリカの核協議
イランの核開発について、アメリカとイランの間で協議が行われていたわけであるが、一つの論調は、この協議が行われているにもかかわらず、そのさなかに、イスラエルがイランを攻撃したことを非難するもので、読売新聞、朝日新聞、東京新聞、西日本新聞、赤旗がそうである。平和的に交渉すべきで、軍事力を持ってすべきではないというのである。
もう一つの論調は、アメリカとイランの間での協議は行き詰まりを見せていたのであり、それに期待を寄せられないから、イスラエルは攻撃したのだというものである。これは産経新聞の主張である。
この交渉に関連して、「イランが米欧中ロなどと結んだ2015年の核合意を一方的に破棄したのはトランプ」大統領であったことを想起すべきであるとするのが朝日新聞である。
その後の展開を見ると、どうやらアメリカは交渉をしながら、イスラエルの軍事攻撃になんらかの形の支持を与えていたようであり、上の両方の見方は修正されなければならないかもしれない。
(4)イスラエルの核保有
イスラエルはイランが核武装することを阻止するために攻撃をしたと言うが、イスラエル自身が核を保有しているのに、そういうイラン批判をするというのは、筋が通らないという批判がある。これは、西日本新聞、信濃毎日新聞、毎日新聞、朝日新聞の社説である。イスラエルは90発以上の核兵器を保有しているというのが、広く認められている情報である。
中でも、「イスラエルは中東で唯一、核拡散防止条約(NPT)に加盟せず、核弾頭を90発保有するといわれる。他国の核開発を理由に攻撃する正当性がどこにあるのか。」と厳しくイスラエルを批判するのが、西日本新聞であり、朝日新聞も、「NPTの枠外で核を持つイスラエルが、NPT加盟国であるイランの核開発を力ずくで阻止することに、国際社会の理解は得られまい。」と批判する。
3. アメリカの「支持」について
アメリカは今回のイラン攻撃には関与していないというが、産経新聞はその言明をそのまま報じている。それに対し、アメリカはなんらかの責任は免れないとするものがあって、アメリカは何らかの支援をしているのでありその責任は重いとする西日本新聞や朝日新聞、アメリカは止められなかったのかとする日本経済新聞、アメリカは黙認の責任はあるとする赤旗がある。東京新聞は、アメリカが「関与」していないなら、イスラエルに「攻撃を中止するよう強く迫るべきではないか」と主張している。
それより注目されるのは、アメリカは事前にイスラエルのイラン攻撃のことを知っていたがイスラエルを「抑え」られなかったとすると、そのことはアメリカの影響力の低下を物語るのであり、アメリカが戦争に巻き込まれるのではないかと心配する読売新聞である。アメリカの責任は別として、イスラエルの後ろにいるアメリカが巻き込まれる可能性があると指摘するのが、信濃毎日新聞である。
その後の展開を見ると、アメリカは「抑え」ようとしていたのかどうか、不明である。表面上は、そういう姿勢を見せているが、水面下ではイランとの協議にも拘わらず、暗黙の支持を与えていたのかもしれず、真相は分からない。しかし、まさに読売新聞の言うように、アメリカは、6月21日、イランの核施設3か所を爆撃し、「戦争に巻き込まれ」、直接交戦国となった。
4. 西欧諸国の態度について
西欧諸国のイスラエルへの態度については、評価の微妙な違いがある。イスラエルのガザ戦争についてもそうであるが、ユダヤ人迫害の歴史を持つ西欧諸国は、ロシアのウクライナ戦争についてはこれを厳しく批判するが、イスラエルのガザやイランへの攻撃についてはこれを批判しないという「二重基準」を適用しているとして、イスラエルのイラン攻撃を黙認し批判をためらっていると指摘するのが、毎日新聞、朝日新聞である。
このような基本的認識の上で、そういう西欧諸国の態度に変化が見られ、イスラエルに批判的になってきていると見るのが、東京新聞、朝日新聞、信濃毎日新聞、赤旗である。それゆえ、離れかかっている西欧諸国を引き戻そうとしているのだと信濃毎日新聞は主張している。
その後の展開を見ると、西欧諸国も、イスラエルを積極的に支持するドイツと、批判的なフランスに二分されてきているように見える。
5. イスラエルの国内問題について
イスラエルがこのような「無謀」な攻撃をしたのはなぜか。これについては、ネタニヤフ首相は対外危機をあおって、国内の団結を図り、自分の政権の延命と維持を狙っているのだとするのが、東京新聞、日本経済新聞、信濃毎日新聞である。他紙は、そういう問題を立てていない。
イスラエル国内では、ガザ戦争などをめぐって、リベラル派と極右との間の対立が激しくなりつつあり、この際、中東全体に問題の舞台を拡げて対立をぼかすという意味もあるようである。その観点から、イスラエルはイランの現体制の転覆までを狙っているのであると指摘するのが、毎日新聞である。その後、この説はさまざまな方面から確認されつつある。
6. 日本のなすべきこと
日本はなにをなすべきか。国際秩序を守るため、外交努力により両国に自制を求めるべきであるというのは、全紙揃っている。そのうえで、信濃毎日新聞は、自衛隊が巻き込まれる恐れがあり、日本経済に影響を与える恐れがあるから、日本は「被爆国として」外交努力をすべきだと言う。ただ、「中東で侵略や植民地支配の歴史のない日本」は、国際的に影響力を行使できるのだと朝日新聞は言うが、「中東」に限って日本の植民地支配の有無を言っても、どこまで国際的に説得力があるであろうか。
またイラン攻撃が日本の石油供給に与える影響を考慮すべきであるとするのが、読売新聞である。そして、イラン戦争の影響で、自衛隊の派遣という問題も出てくると指摘するのが、それぞれの立場は違うが、産経新聞と信濃毎日新聞である。
次回は、アメリカによるイラン攻撃について、同じように各紙の社説を比較してみたい。