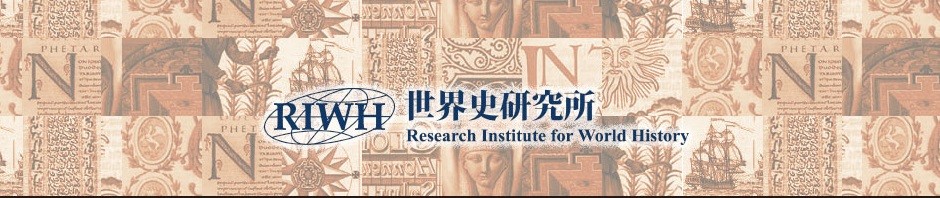「植民地主義」
2023年11月7-8日に日本で行われたG7プラスの外相会議で、議事の重要な柱として、パレスチナでの戦争について話が行われた。会議はハマスを非難した後、早期の休戦や人道的救済などについて合意した。その会議後、8日に外人記者クラブでの会見で、アメリカのブリンケン国務長官は、G7会議での合意を説明した後、ガザとパレスチナの戦後の体制について、こういう趣旨の発言をした。
米国は、ガザからのパレスチナ人の強制退去、ガザをテロの温床にすること、戦後のガザを再占領すること、ガザを封鎖したり包囲すること、ガザを地域的に縮小することは望まない。平和を持続させるためには、危機後のガザの統治の中心にパレスチナ人の声と願いが置かれなければならない(the Palestinian people’s voices and aspirations at the center of post-crisis governance in Gaza)。それは、パレスチア人の率いる政府であり、パレスチナ人政権のもとでガザを西岸と合体することである(Palestinian-led governance and Gaza unified with the West Bank under the Palestinian Authority)。そうして、イスラエル人とパレスチナ人が自分自身の国家を持って共存し(Israelis and Palestinians living side by side in states of their own)、同じような安全と、自由と機会と尊厳をもつようにするべきである、と。(https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-a-press-availability-41/)
これを受けて、ローデシアのジャーナリストTafi Mhakaは、Aljajeeraの12月15日付Opinion「アフリカはパレスチナについての西の植民地ゲーム・プランに反対しなければならない(Africa must challenge the West’s colonial game plan for Palestine)」において、G7東京会議は、ビスマルクが主催した1883-4年の西アフリカ・ベルリン会議のようだと批判した。つまり、パレスチナにせよ西アフリカにせよ、ともに当事者のいないところで、当事者たちの統治形態を議論しているというのである。植民地史上「悪名高い」ベルリン会議は原住民の意向を考慮すると言いながら、会議に原住民を一人も呼ばなかったではないか。かれは、これは「植民地主義」にほかならないという。パレスチナ人の「自決権」などブリンケンは触れもしなかった。
そのうえで、Tafi Mhakaは、アメリカが提案しているように、ガザをヨルダン川西側と合わせて、「パレスチナ人を代表する政権」の統治下に置くという事は、西岸のアッバス政権の統治下に置くということにほかならず、その方式には反対だという。それは、極めて「人気のない」「無能の」アッバス政権は、アメリカなどの「傀儡政権」にほかならないからだと言う。これは「植民地主義」の手段にほかならないというのである。
Tafi Mhakaは言う。パレスチナ人には自分が好む政府を選ぶという民主主義的権利があるのだ。G7はハマスを排除した新たな政治体制と政治システムを押し付けるべきではない。パレスチナにおける民主主義というのは西の(そしてイスラエルの)要求と同義語であってはならない。
ハマスは2006年の議会選挙でアッバスのファタハ党を破ってからガザを統治してきていた。だが、その時以来、西側諸国は、ハマス政府を転覆して、ガザをファタハの支配下に戻そうと共謀してきた。それはブッシュ政府のもとで数回試みられた。こういう不法な計画は失敗したが、今日また、米国とその強力な同盟諸国は、ふたたび、ハマスを排除し、占領されたパレスチナ人の土地をすべて、イスラエルに友好的な傀儡政府の下に置こうとしている。名前だけはパレスチナだが、実際には植民地列強(colonial powers)の言いなりになっている政府の手にパレスチナを委ねることは、持続的な平和と正義をもたらしはしない。
このように述べた後で、Tafi Mhakaはアフリカ人としてこう述べた。
「アフリカ人として、われわれは、そのような新植民地主義の傀儡政府がすぐにつぶれて新たな流血を生んだり、あるいは暴力や抑圧や外部からの支援を得て長らく政権にとどまったりしていることを知っている。後者のような政府は、その植民本国の名で統治する領土を、腐敗と人権侵害と極度の貧困と大規模な失業の沼地にしてしまっている。その沼地は、きれいにするには、国民的政府が、数十年とは言わぬまでも長い年月を必要とするのである。」(https://www.aljazeera.com/opinions/2023/12/15/africa-must-challenge-the-wests-colonial-game-plan-for)
上で見たような意見は、アフリカの一ジャーナリストの意見であるが、「ガザ戦争」を別の角度から見る場合の参考になることは間違いがないであろう。
もちろん、イスラエルのネタニヤフは、上のブリンケン発言とも違って、戦後の「ガザ」について、それのイスラエルによる「管理」を主張しているのであるから、アフリカの人はさらに憤りを懐くであろう。
(南塚信吾)
木畑洋一
イスラエル批判と反ユダヤ主義